アゲハ飼育日誌2020年第40稿:
このところ、寄生虫づいている気がしますが、気のせいでしょうか。
今回も後ろ半分はそういう話です。
吐糸
2020.8.13
ご存じの方が多いと思いますが、アゲハの幼虫は糸を吐きながら移動します。
こんなふうに。
かなり広範囲に糸を張り巡らします。
このように糸を吐いて足場を作るので、

つるつるのガラスでも難なく張りつけるわけです。腹脚だけでくっついているわけではありません。
幼虫がいなくなったあとのガラス面はこうなっていました。
ビンに張り付くだけならこの程度ですが、蛹になる場所の足場はこんなものではありません。もっとびっしり張り巡らします。
恥ずかしいことに、今頃になってわかったのですが、糸は口から吐いているわけではないんですね。口の下にある吐糸管(としかん)から吐いています。
因みに糸を吐くことを吐糸(とし)と言います。当サイトではこれまで「糸吐き」と書いていました。
これからは吐糸と書きます。
ハマキムシ
2020.8.15
餌用のクスノキに、また得体のしれない虫がいました。

何という虫かわかりますか?
チャハマキ。ハマキムシ(ハマキガの幼虫の総称)の一種です。
調べてもわからず、Yahoo!知恵袋で教えてもらいました。
葉っぱを巻いて中に隠れることが、ハマキムシと呼ばれる所以とのこと。うちのチャハマキもそうしていました。
きっとクスアオシャクもこうやって葉っぱをくっつけていたのでしょう。
いろいろな虫がいますね。
初の寄生
2020.8.15
ついにクロアゲハが寄生虫の犠牲になりました。
我が家のアゲハ飼育史上初めての出来事。と言っても、5年くらいですが。


ここからヤドリバエの幼虫が出現。
これまでうちのクロアゲハが寄生されなかったのは、単に数が少なかったからでしょう。
今年の日誌36稿 に書いた穴場を発見して以来、数が増えてきたらやっぱり駄目でした。
クロアゲハが特別強いわけではないということです。
寄生後
2020.8.9~15
寄生虫が出てきたナミアゲハの幼虫( 前回の日誌 )は、その後どうなったかと言うと、3日生きていました。

このように傷口はかさぶた(?)でふさがれたので、持ち直さないかと期待しましたが、餌を食べることなく死にました。
寄生虫のほうはどうなったかと言うと、繭がパカッと割れて、お目見え。
ハエのような動きをしますね。
我が家で寄生バチが羽化したのは初めて。
何という蜂かわからず、こんなツイートをしました。
ナミアゲハから出てきた寄生蜂が羽化しました。🐟
何という蜂か、ご存じの方教えていただけますか❓#寄生 #寄生蜂 #蜂 #昆虫 pic.twitter.com/AhyYyDGDWv— たむら船堀 (@fo180926) August 17, 2020
正解は、必殺料理人さんの返信にあるギンケハラボソコマユバチのようです。
こんな追伸もいただきました。
— たむら船堀 (@fo180926) August 18, 2020
ありがとうございました‼
あとで気づきましたが、ギンケハラボソコマユバチは 昨年の日誌47稿 に書いてある候補の1つでした。
1年越しで答えがはっきりしてよかった。
2020/8/18,2022/2/12
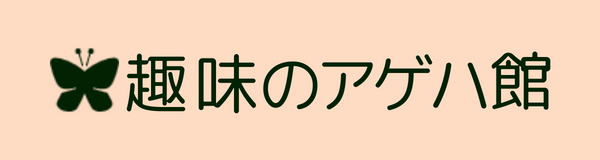

コメント