「アゲハチョウが蛹から蝶になるまでの期間てどれくらい?」「アゲハチョウの蛹は何色?」「蛹になる場所はどこ?」。そんな疑問がありますか?
あるいは「幼虫が蛹になる時にはどんな変化があるんだろう」「飼い主は何をしたらいいんだろう」と思っているところでしょうか。
アゲハチョウの飼育で最も気を遣うのは蛹化の時。飼い主が注意を怠ると、まともに羽化できなくなるかもしれません。
我が家では長年の飼育経験によって、蛹に関する知見が増し、蛹化時のトラブルにも対応できるようになりました。
この記事ではアゲハチョウの蛹に関する基本的な情報に加え、幼虫が蛹になるまでの期間における注意すべきポイント、蛹が落ちた時の対策、蛹が羽化しない理由、蛹の越冬について解説します。
これらの点がわかれば、飼い主が戸惑うことはなくなるでしょう。
- アゲハチョウの蛹の期間や色
- アゲハチョウが蛹になる場所
- アゲハチョウの蛹化における3つのポイント
- 蛹が落ちた時の対策と羽化しない理由
アゲハチョウの蛹に関する基本情報
まず、アゲハチョウの蛹に関する基本的な情報を書いておきます。
蛹から蝶になるまでの期間
アゲハチョウの蛹の期間は概ね以下のとおりです。
通常サイズ(ナミアゲハ、アオスジアゲハなど): 1週間から10日
大型サイズ(クロアゲハ、ナガサキアゲハなど): 2週間前後
気温が低くなると、それなりに期間は長くなります。越冬蛹は暖かくなるまで数か月、蛹化の時期が早ければ半年以上休眠することもあります。

越冬蛹に関しては後述します。
蛹の色は茶色か緑色が多い
蛹の変色には様々な要素が関係しますが、一部の例外の除き、ほとんどの蛹は茶色か緑色系統になります。

ナミアゲハ

アオスジアゲハ

クロアゲハ
例外はこれ。


ジャコウアゲハ
黄色。越冬蛹(右)は薄茶色。
蛹の変色に関する詳しい情報はこちらの記事でご覧ください。
蛹になる場所は割り箸とは限らない
幼虫は蛹になる場所を予め決めているわけではありません。ほとんどの場合は食草を離れて蛹化します。
どこに行くかわからないので、家飼いでは虫かごやダンボール箱に閉じ込める人が多いでしょう。割り箸を貼っておいても、そこで蛹になるかどうかわかりません。

蛹化時の移動に関しては後述します。
脱走されると探すのに一苦労です。
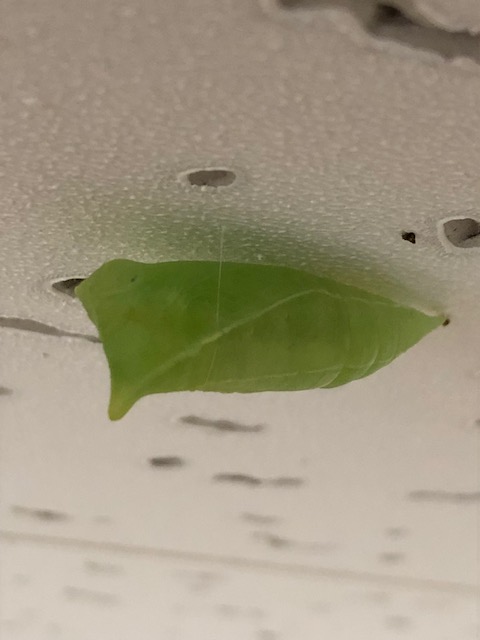
天井に張り付いていたアオスジアゲハの蛹。

小物入れの中の袋に張り付いていたナミアゲハの蛹。
その点、アオスジアゲハは幾分楽です。

大抵はこのように食草の中で蛹化します。但し、適切な角度の葉っぱが無いと脱走しますので、ご注意ください。
蛹は全く動かないわけではない
蛹も動きます。
と言っても、動くのは好ましいことではありません。特に蛹化後4,5日は体の形成期なので、そーっとしておきましょう。
こちらの記事に動く蛹の動画があります。
よく動くのは蛹になりたての頃と、羽化が近づいた頃です。その間はあまり動きません。
というわけで、動かないから死んでいるというのは早計です。
アゲハチョウの蛹化におけるポイント
ここではアゲハチョウの蛹化における3つのポイントと不測の事態などについて述べます。
ポイント1: 蛹になる場所への移動
最初のポイントは蛹になる場所への移動。
終齢幼虫は蛹になる時が来ると葉っぱを食べなくなり、おしりを下に向けて、ひたすら糞をします。
糞の形状は徐々に変化します。詳しくは こちらの記事 をご覧ください
最後に液状便をすると、幼虫は蛹になる場所を求めてさまよい始めます。そうなったら、放置しておいてはなりません。
どうしたらいいのか。こちらの記事でご覧ください。
ポイント2: 前蛹になる時の糸掛け
2つ目のポイントは前蛹になる時の糸掛けです。
ここではトラブルがない限り、何もする必要はありません。
蛹になる場所が決まった幼虫は、しばらくすると頭部の接触面に糸を張り巡らします。その後180度回って下を向き、お尻を固定する所に大量の糸を吐きます。
これはお尻を固定する場所に糸を吐いているところ。
このあと180度回って、元どおり上を向きます。

糸を張り巡らした後の幼虫。
すでにだいぶ縮んでいますが、
このように、さらに体を縮めていきます。

こうなりました。
このあとしばらくすると、幼虫は帯糸(胸部を固定する輪っか)を作り、そこに頭をくぐらせます。
全行程は10分以上かかるので、動画は最後の3分だけにしました。
幼虫は帯糸が風雨にさらされても切れないようにするため、入念に糸を重ねます。

糸掛け完了直後。

がんばった。
ポイント3: 蛹になる時の脱皮
3つ目のポイントは蛹になる時の脱皮です。
ここでもトラブルがない限り、何もする必要はありません。

糸掛け翌日7時19分
我が家では可能な場合、前蛹を観察しやすい場所に移します。今回は羽化用に準備したエッグスタンドに移しました。
同日22時48分 1匹目の脱皮
同日23時3分 2匹目の脱皮

蛹化完了。

翌朝。別の1匹と共に、いい具合の枯れた色になっていました。

お疲れさま。
蛹が蝶になるまでの行程はこちらの記事でご覧ください。
蛹が落ちた時の対策
帯糸が切れたり、おしりの固定が外れたりして蛹が落ちる、あるいは宙ぶらりんになることがあります。そのまま放置しておくと、まともに羽化できません。
そういう場合は、蛹を蛹ポケットに入れるか、ティッシュペーパーや布に置くようお勧めします。
やり方はこちらの記事でご覧ください。
蛹が羽化しない理由
蛹が羽化しない理由は4つ考えられます。
これらは外見でわかる場合とわからない場合があります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
蛹が越冬する時の処理
アゲハチョウの蛹が越冬するかどうかは、若齢幼虫時の日長(家飼いの場合は照明時間)と蛹の飼育環境(おもに気温)で決まります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
アゲハチョウの蛹【まとめ】
以上、アゲハチョウの蛹についていろいろ書きました。
ポイントは以下のとおりです。
アゲハチョウにとって蛹化は大事な工程。生涯で最も難しく、最も重要な工程と言えるかもしれません。前蛹がしっかり固定されていないと脱皮に失敗したり、まともに羽化できなかったりするかもしれないからです。
実際に我が家では、蛹になる脱皮の最中に帯糸が上にずれてしまったり、おしりの固定が外れてしまったりした個体がいました。いずれも蛹ポケットで無事に羽化しましたが、自然界なら羽化不全になるか、死んでいたでしょう。

自然界でアゲハが羽化する確率は1~2%。いろいろあります。
アゲハチョウに関する総括的な情報は、こちらの記事でご覧ください。
2018/8/31,2024/5/13
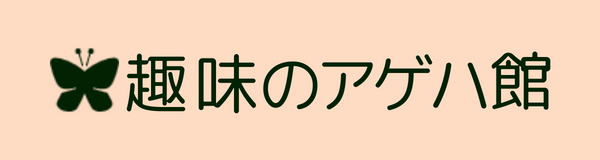







コメント