アゲハチョウの幼虫を育てていて、フンの形状が変わることに気づきましたか? 幼虫の成長過程はフンを見ればわかります。フンの変化に気づかないと、適切な世話を行えません。
この記事をご覧になれば、そんな疑問の答えが得られます。アゲハチョウの飼育にお役立てください。
アゲハチョウの幼虫 フンでわかる成長過程
フンの基本形は3種類
アゲハチョウの幼虫がするフンの基本形は3種類あります。

①乾いた黒いフン
②湿った緑のフン
③液状のフン

②は①より大きくなります。
フンの色合いは食べている葉っぱによって異なります。

このとおり、色とりどり。
我が家ではこのようにフンを取っておいて、鉢植えの肥料にしています。
固形のフンには大きなくぼみがあります。理由は こちらの記事 でご覧ください。
液状のフンは以下のとおり。

柑橘で育ったナミアゲハのフン

山椒で育ったナミアゲハのフン

ウマノスズクサで育ったジャコウアゲハのフン
では、幼虫の成長に伴い、フンの形状はどのように変化するのでしょうか。
成長に伴うフンの変化
幼虫のフンは終齢になるまで硬く、蛹化が近づくにつれて柔らかくなり、ガットパージ(幼虫最後の排泄)では液状になります。
- 1齢~終齢幼虫前半: 硬いフン(前述①)
- 終齢幼虫後半: 硬いフンから徐々に柔らかいフン(前述②)に変化
- ガットパージ: 液状のフン(前述③)
ということなので、終齢幼虫の後半になったら、単独で育てるといいでしょう。
我が家ではこうしています。

こうしておけば、フンの形状の変化がわかるので、ワンダリング(蛹化の場所決め)に備えることができます。

なるほど。
ガットパージからワンダリングまでの世話に関しては、こちらの記事をご覧ください。
✔ アオスジアゲハは例外:
アオスジアゲハの幼虫が液状便をすることはほとんどありません。最後はこういうフンをします。

これは4匹分。黒いフンは直径3mm、カラフルなフンは直径1mmほど。
ワンダリングの前に湿った黒いフンをして、場所が決まってから最後にカラフルなフンをします。

カラフルなフンはしない幼虫もいます。
危険信号となるフン
危険信号となるフンがあります。
例えば、

ガットパージではない時の液状便。
ウィルスや細菌に感染しているかもしれません。と言っても、致命的ではない場合もあります。
あとは、

連なるフン。

7連は超珍しい。
病害か薬害か。この幼虫は蛹になることなく死にました。
幼虫は密集、高温多湿を避け、風通しの良い場所で育てましょう。フンの始末はこまめに。衛生状態が悪くなると、細菌やウィルスの感染を招きます。
虫かごで育てる場合はこちらの記事を参考になさってください。
アゲハチョウ幼虫のフン【まとめ】
以上、アゲハチョウ幼虫の成長に伴うフンの変化、それに合わせた世話、危険信号となるフンについて書きました。お役に立てば幸いです。
当サイトではアゲハチョウ幼虫の排泄物を「糞」と称していますが、検索のキーワードは「フン」になっているため、この記事では「フン」にしました。
アゲハチョウに関する総括的な情報は、こちらの記事でご覧ください。
2021/7/31,2024/5/25
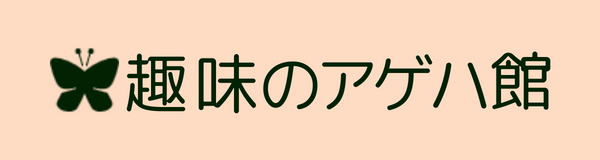



コメント