アゲハ蝶の幼虫って、どんなふうに成長するの? 幼虫の種類って、簡単に見分けられるの? 活動時期はいつ頃? 何を食べるの? どうやって育てたらいいの? そんな疑問がありますか?
アゲハチョウは身近な昆虫ですが、育てるとなるとそれなりの知識が必要です。飼育は難しくありませんが、幼虫の習性を理解していないと、最悪の場合死なせてしまうかもしれません。
我が家では毎年アゲハ蝶の幼虫をたくさん育てていて、いろいろなことがわかりました。
この記事ではアゲハ蝶幼虫の成長過程、種類、活動時期、食べる葉っぱ、見分け方、育て方などの基本的なことだけでなく、餌の食べ方やおもしろい習性についても解説します。
最後までご覧になれば、幼虫に関する大方の疑問は解消するでしょう。
- アゲハ蝶の成長過程、種類、活動時期など
- アゲハ蝶幼虫の見分け方、育て方
- 幼虫の餌の食べ方やおもしろい習性
- 幼虫が成虫になるまでの様子
アゲハ蝶の幼虫徹底解説
ここではアゲハ蝶幼虫の成長過程、種類や活動時期、食草(食べる葉っぱ)など基本的なことから、見分け方、育て方、おもしろい習性に至るまで詳しく解説します。
幼虫の成長過程
まず、アゲハ蝶幼虫の成長過程を見てみましょう。
アゲハチョウは完全変態する昆虫。孵化した幼虫は通常4回(ごく稀に5回)脱皮して齢数を重ね、蛹を経て成虫になります。
ナミアゲハの卵が成虫になるまでの成長過程は以下のとおり。
卵の期間
卵の期間: 3~5日

大きさ: 1mm前後
産卵直後の卵は透き通るような黄色。やがて幼虫の影が現れ、孵化します。その間も寄生される危険があります。
卵に関する詳しい情報、孵化の動画はこちらの記事でご覧ください。
1齢幼虫の期間
期間: 2~4日

大きさ: 2~5mm
孵化直後は黄土色。徐々に茶色が濃くなり、中央に白い筋が見え始めます。
2齢幼虫の期間
期間: 3~5日

大きさ: 5~10mm
中央の白い線が目立つようになり、鳥の糞ぽくなってきます。

擬態ですね。
3齢幼虫の期間
期間: 3~5日

大きさ: 10~20mm
突起が目立つ(脱皮直後は黄色が強い)ようになります。
4齢幼虫の期間
期間: 3~5日

大きさ: 15~25mm
全体的に黒っぽい緑色になります。
こんな感じで脱皮して、5齢幼虫に変身。
5齢幼虫の期間
期間: 5~7日
クロアゲハなどの大型種はプラス数日。

大きさ: 20~45mm
終齢幼虫(幼虫の最終形態)は通常5齢幼虫ですが、ごく稀にもう一度脱皮して6齢幼虫になることがあります。
5齢幼虫になると、寄生される確率が格段に上がります。寄生バエや寄生バチに発見されて、表皮や周囲の葉っぱに卵を産み付けられるからです。

かわいそう。
アゲハチョウの寄生虫に関しては、こちらの記事をご覧ください。
前蛹の期間
期間: 1~2日

5齢幼虫が糸掛けをして、くの字になった状態。
こうなった当日か翌日には脱皮して蛹になります。
蛹の期間
期間: 7~10日
クロアゲハなどの大型種はプラス数日。越冬蛹ならプラス越冬期間。

終齢幼虫は蛹化の時期になると、ガットパージ(余分な体液の排泄)、ワンダリング(蛹化の場所探し)の後、糸掛けをして前蛹になり、生涯最後の脱皮をして蛹になります。
その一連の行動に関しては、こちらの記事をご覧ください。
成虫の期間
期間: 2週間以上
室内飼育の場合はもっと長くなります。特に冬期はあまり動かないため長生きし、我が家では最長2か月ほど生きました。3か月以上生きたという話を聞いたこともあります。

こんな感じで羽化します。

揺れちゃって、すみません。
成虫はペアリングの相手を求めて飛び回り、雌は死ぬまでに200個ほど産卵します。
卵から成虫になるまでの期間
卵から成虫までの期間をまとめるとこうなります。
| 卵の期間 | 3~5日 |
| 1齢幼虫の期間 | 2~4日 |
| 2齢幼虫の期間 | 3~5日 |
| 3齢幼虫の期間 | 3~5日 |
| 4齢幼虫の期間 | 3~5日 |
| 5齢幼虫の期間 | 5~7日 |
| 前蛹の期間 | 1~2日 |
| 蛹の期間 | 7~10日 |
| 成虫の期間 | 2週間以上 |
卵から成虫になるまでの期間は約1か月
クロアゲハなどの大型種はプラス1週間から10日前後かかります。
幼虫の種類,時期,食べる葉っぱ
日本国内を分布域とするアゲハチョウの種類を知っておきましょう。
種類ごとの分布域、活動時期、食べる葉っぱは以下のとおりです。
ナミアゲハ
並揚羽(学名: Papilio xuthus)
全国的に最もよく見られるアゲハチョウ。「ナミアゲハ」は俗称で、「アゲハ」、「アゲハチョウ」と呼ばれることが多い。
| 分布域 | 国内全域 |
| 活動時期 | 4~10月 |
| 食草 | ミカン科植物(ミカン,レモン,サンショウなど) |






クロアゲハ
黒揚羽(学名: Papilio protenor)
大型のアゲハチョウ。1,2齢幼虫は胸部に2本突起がある。穏やかな性格でおっとりしている。
| 分布域 | 本州以南 |
| 活動時期 | 5~10月 |
| 食草 | ミカン科植物(ミカン,レモン,サンショウなど) |






アオスジアゲハ
青条揚羽(学名: Graphium sarpedon)
成虫の翅が色彩豊かなアゲハチョウ。幼虫はずんぐりした形。2,3齢幼虫は胸部が黒ずむ。街路樹にクスノキを多用する関東都市部に多い。
| 分布域 | 東北南部以南 |
| 活動時期 | 5~10月 |
| 食草 | クスノキ科植物(クスノキ,タブノキ,ニッケイなど) |






キアゲハ
黄揚羽(学名: Papilio machaon)
ナミアゲハと並んで広く知られるアゲハチョウ。幼虫は全身縞模様で派手な外見。
| 分布域 | 国内全域 |
| 活動時期 | 4~10月 |
| 食草 | セリ科植物(パセリ,ミツバ,ニンジンなど) |




ジャコウアゲハ
麝香揚羽(学名: Byasa alcinous)
国内で唯一毒を持つアゲハチョウ。終齢幼虫も黒い変わり種。餌が無くなると共喰いする。
| 分布域 | 本州以南 |
| 活動時期 | 5~10月 |
| 食草 | ウマノスズクサ科植物(ウマノスズクサ) |






ナガサキアゲハ
長崎揚羽(学名: Papilio memnon)
国内最大級のアゲハチョウ。1~3齢幼虫は胸部に2本突起がある。成虫は翅に尾状突起がない。
| 分布域 | 関東以南 |
| 活動時期 | 5~10月 |
| 食草 | ミカン科植物(ミカン,レモン,サンショウなど) |






モンキアゲハ
紋黄揚羽(学名: Papilio helenus)
ナガサキアゲハと並ぶ国内最大級のアゲハチョウ。幼虫はクロアゲハと酷似。4齢になると黄色い斑点が目立ち始める。
| 分布域 | 関東以南 |
| 活動時期 | 5~10月 |
| 食草 | ミカン科植物(ミカン,レモン,サンショウなど) |


その他
その他国内で観察できるアゲハチョウは以下のとおりです。
✔ カラスアゲハ
✔ ミヤマカラスアゲハ
✔ オナガアゲハ
✔ シロオビアゲハ
✔ ミカドアゲハ
✔ ベニモンアゲハ
残念ながら我が家でこれらの飼育経験はなく、自前の画像がありません。
画像その他の情報はこちらのサイトでご覧になれます。
幼虫の見分け方は色や模様や形で
前掲の画像とおり、ほとんどの幼虫の色は若齢が黒、終齢が緑です。
アゲハ蝶の幼虫は齢数にかかわらず、色も模様も形も多様。そこに規則性があるわけでもありません。
私が参考にしているのは 蝶の幼虫図鑑 です。他のサイトに比べ、若齢も終齢も画像の数が多いので助かります。
代表種ナミアゲハとクロアゲハの見分け方は、こちらの記事でご覧ください。
幼虫の育て方は難しくない
幼虫の飼育は難しくありません。必要なものは幼虫を入れる容器と餌、蛹化時に使う枝や割り箸ぐらいです。
飼育するのであれば、以下の点を押さえておきましょう。
具体的な飼育方法はこちらの記事でご覧ください。
幼虫は共食いする?
ジャコウアゲハの幼虫は餌がないと共喰いします。
ほかはどうか。基本、共食いはしませんが、絶対しないというわけではありません。
滅多にないことですが、狭い空間で体格差がある幼虫を飼育していると、共食いすることがあります。
こちらの記事をご覧ください。
幼虫の餌の食べ方
幼虫の餌の食べ方はユニークです。
クロアゲハは几帳面
クロアゲハは柑橘類の葉っぱをこんなふうに食べます。
まず、主脈(葉っぱ中央の太い葉脈)の片側だけを付け根のほうから食べます。
その後、残った片側を同じように食べます。

几帳面。
最後に残った主脈はこうします。
時間がかかるので早送り。なんでここまで苦労して主脈を切り落とすのか。
おそらく、食痕を残さないため。つまり天敵に居場所を突き止められないようにするためです。
ナミアゲハは芸術的
ナミアゲハも基本的に同じ食べ方をしますが、主脈は切り落としません。

面倒臭いことはしないたちか。(笑)

山椒の葉っぱはこのように手前から1枚ずつ平らげていきます。
そのため、枝ぶりがこんな芸術的な形に。




我が家ではこれを“生け青虫”と呼んでいます。
アオスジアゲハは早食い
アオスジアゲハはやみくもに早食い。前者のような几帳面な食べ方はしません。

速い‼
クスノキの葉っぱは柔らかいためか、主脈も一緒に一気食い。他の幼虫と比べると食べるスピードがやたら速く、早送りの動画を観ているようです。
それでも用心深く、すごい勢いで食べていても、周りで物音がすると食べるのをやめます。しばらくそのまま動きません。

臆病者。
食べ残した葉っぱはこうします。
葉っぱの付け根まで戻り、食べ残した葉っぱを切り落とします。
あとで食べればいいのに。

もったいない。
なんでこうするのか。
これもおそらく食痕を残さないため。防衛策です。

幼虫のおもしろい習性
餌の食べ方以外にも、おもしろい習性がいろいろあります。
餌場とホームは別
幼虫は基本、餌場とホーム(摂食時以外の居場所)を別にします。
つまり、自分のホームにする葉っぱを決めていて、空腹になるとそこから出掛けていって餌を食べ、食べ終わるとホームに戻ってくるということ。
ホームに戻ってくると、葉っぱ全体を一度巡回します。留守中に異変が起きていないかどうか、確認しているのかもしれません。

用心深いね。
それから定位置に鎮座。
ホームにしている葉っぱの中なら、どこでもいいわけではないようです。

ホームで休憩中。
このように食痕から離れた所で落ち着くのも、おそらく防衛本能でしょう。
大きくなるとホームを独占
体が小さいうちは、

このようにホームを共有していますが、大きくなってくると独占したがります。
ホームに侵入者が入ってくると、こうなります。
すごい剣幕ですね。
でも、こういうこともあります。


仲良く同居? それとも追い出せなかったのか。
でも、これは一時的です。
糞を遠ざける
当然ながら、ホームにしている葉っぱではよく糞をします。
糞が下に落ちればいいのですが、葉っぱに乗ったままだと、
吹っ飛ばします。

手際じゃなくて”口際”がいい。
これはホームに限ってのことではありません。
食べている途中で気づきました。
近くに糞がたくさんたまっていると、わざわざ降りてきて片づけることも。
これはナガサキアゲハの4齢幼虫。

かみさんが意地悪をして糞を寄せています。
これもおそらく居場所を突き止められないようにするためです。
脱け殻を食べる
幼虫は脱皮した後、脱け殻を食べます。
これはクロアゲハ4齢幼虫の脱皮。
最後に口から出したように見えるのは、頭部の抜け殻。
このあと戻ってきて脱け殻を食べます。
完食。孵化した後は卵の殻を食べます。
これはナミアゲハ。
無駄を出さないクリーンなエコロジー。
栄養補給と共に、これも居場所を知られないようにするためでしょう。
幼虫のかわいい画像・動画
ここまでご覧になってどうでしょう。アゲハ蝶の幼虫はかわいいと思いませんか?
当サイトで掲載しているアゲハ蝶幼虫のかわいい画像と動画を種類ごとにまとめました。
こちらの記事をご覧になってみてください。
アゲハ蝶の幼虫が成虫になるまで
以上、アゲハ蝶の幼虫についていろいろ書きました。
終齢幼虫が前蛹になり、前蛹が脱皮して蛹になり、羽化して蝶になる様子も載せておきます。
幼虫の糸掛け【終齢幼虫~前蛹】
終齢幼虫は蛹化ホルモンが出ると、蛹になりやすい場所を決めて体をとめる糸を掛けます。
これはナミアゲハの糸掛け。
最後の糸をくぐるところ。糸掛けは20~30分かかります。

前蛹になりました。
前蛹の脱皮【前蛹~蛹】
前蛹は1~2日経つと脱皮します。
前掲と同じナミアゲハの脱皮。
脱皮は7~8分かかります。

脱皮後間もない蛹。

擬態完了後の蛹。
羽化【蛹~成虫】
ナミアゲハ、キアゲハなど普通サイズのアゲハチョウは蛹化後概ね7~10日、クロアゲハなどの大型種は10~14日で羽化します。
これはクロアゲハの羽化。

気持ちええやろなぁ。
アゲハ蝶の幼虫【まとめ】
以上、アゲハ蝶の幼虫を育ててわかったあれこれについて書きました。
ポイントは以下のとおりです。
ちっぽけな虫でも、観察しているといろいろな発見があっておもしろいですね。興味は尽きないというほどではありませんが、昆虫学者の喜びが少しわかったような気がします。

ほんまか。
2018/2/24,2024/6/11
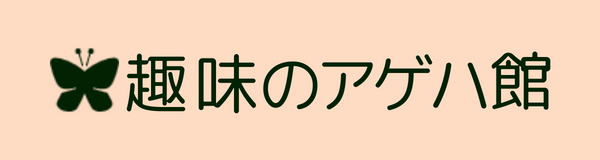








コメント
こんにちは。はじめまして。
2週間前からナミアゲハの幼虫を飼い始めました。
大変素晴らしいブログ、参考にさせて頂いてます。
今、飼育ケースのフタと本体をまたぐような場所で前蛹化してしまい、フタが開けられず、ケースの掃除ができなくなってしまいました。
一日前から残っているフン(下痢含む)と山椒の葉が数枚残っているのですが、このままにしていても問題ないでしょうか?
それは厄介な所で定位しましたね。そのままでも問題ないと思いますが、羽化した時に落ちそうなら、前蛹をコーンに入れるといいでしょう。
前蛹を外す時は、台座(張り巡らされた糸)をセロテープでペタペタやればきれいに剥がせます。こちらの記事 にある蛹ポケットの動画を参考にしてください。同じ記事に前蛹コーンの作り方の動画もあります。
さっそくのコメントありがとうございました。
もし落下したら蛹ポケットは蛹に触る勇気がないので、寝かせ方式にしようかと思います。
羽化まで約10日間もかかるので、フン放置は衛生的に問題ないかが心配ですが、一旦放置してみますかね。。
先日、同じ木から取ってきた終齢幼虫が2匹ともヤドリバエに寄生されてて悲惨な状態でしたが(こちらのブログのおかげでそれに気づくことができました。)、
今育ててるほうは、4齢から育ててるのでまだ望みがあるといいんですが。(終齢は寄生されてる確率が高いとのことだったので。)
先日 黒と透明、白い爪のようなものが2つ
何でしょう? の質問をしたものです。
解答が、ここにありました!
前蛹の脱皮の脱殻です。
今までは、糞の中に紛れていて、気づかなかったようです。
今回は、全て蛹になっていて、糞は片付けた後なので発見できたようです。
お騒がせしました。
昨年から孵化を試みています。
回を重ねるごとに発見があり、生き物の生きるということに感動してしています。
手探り状態のときにココを知りました。たくさん参考にさせていただいています。ありがとうございます。
見方がわかったので、インスタとYouTubeでフォローさせていただきます。
これからもよろしくお願いします。
いえいえ、とんでもない。答えが見つかってよかったです。
こんにちは。
サイト、いつも有り難く参考にさせて頂いています。
元気に成長していた幼虫が蛹化の途中で失敗している模様です。何故か下半分だけ脱皮してしまい、上半分の皮が残ってしまいました。霧を拭いてふやかして、なんとか取れるだけの皮はピンセットで外したのですが、肝心な頭の部分がどうにもなりません。無理をして傷つけては不味いと思うのですが、お面の部分とその下の節の間に大きなくびれがあるままにお面部分の皮が硬くなってしまっています。もしも救済の方法をご存知でしたご教授頂けないでしょうか?
そうなってしまったら放置するしかないと思います。もしかしたら生き延びるかもしれません。
小学校1年の息子がナミアゲハの幼虫を捕まえて来て、飼育中です。
いつ蛹になるかなぁと様子を見ていたら、枝を行ったり来たり、逆さになったりし始め、何だろうと調べてこのブログに。分かりやすく、何より面白く、笑いながら読んでいて、ふと我が家の幼虫を見たら体に糸を付けようとしていて感動!挿入してあった動画を感激しながら見ていた最中だったので、同じ状況にまた感動。思わず、コメントをしています。うちの子は、糸を何度も何度も行き来してどんどん強くなっているようで、応援しながらのコメント書きです。幼虫の綺麗さと可愛い動きにメロメロです。情報をありがとうございました。ちなみに、糞吹っ飛ばし画像に爆笑しました。
それはグッドタイミングでしたね。アゲハチョウの飼育はお子さんの情操教育にうってつけでしょう。
笑いと感動をお届けできてよかったです。糞飛ばしは こちらの記事 にも幾つかありますので、ご覧になってみてください。
励みとなるコメント、ありがとうございました。
コメントを書かせていただいている間に羽化してました!
こちらは東海ですが、今は風が強いです。台風でも早くケースから出して放したほうが良いでしょうか?
羽化しても翅が乾くまで、少なくても3時間程度は飛べません。自分から飛ぶまで待ったほうがいいのですが、台風の最中に放すのはかわいそうですよね。私なら台風が通り過ぎてから放します。
いつもありがとうございます。
アゲハの幼虫のためにレモンの葉を採集した時に、葉にくっ付いていた幼虫をそのまま飼育していました。初めは、他のナミアゲハの幼虫と変わりなかったのですが、だんだん身体の表面に光沢が出てきて、模様や形が一匹だけ野生的になってきました。他の五令より大柄ですし。自然の中で孵化した子なので個性的に育ったと思っていましたが、こちらのナガサキアゲハの幼虫の画像を見たらそっくりです。ナミアゲハの幼虫は飼育ケースで孵ったせいか、一度もツノを出したことがありません。その異質な幼虫はすぐに威嚇していましたが、私を覚えてくれたのか葉っぱで触っても怒らなくなりました。
蛹が一つ、頭のほうから黒くなってきました。台風が過ぎたあとに羽化となりそうで、ほっとしてます。