アゲハ飼育日誌2019年第20稿:
昨日ついに連続投稿が途切れました。15日連続で終わりです。それでも、相撲なら全勝優勝。よくやりました。(笑)
今回はちょっと、ためになる話から。
落ちた卵
2019.6.24
餌用の柑橘類をまとめていたら、ナミアゲハの卵が1つ落ちていました。
葉っぱから落ちた卵は、もうくっつきません。葉っぱに乗せるだけでは固定されないので、孵化する時に支障が出るでしょう。
そこでかみさんはどうしたかと言うと、片栗粉(水でといて過熱)でくっつけました。

もともと葉っぱに付いていた面は幾分平らになっているので、その面を下にしてくっつけます。
片栗粉の原料は精製したでんぷんです。
葉っぱが光合成で作り出す養分の1つがでんぷん。アゲハチョウの卵の成分は何だかわかりませんが、相性が悪いことはないでしょう。孵化した幼虫は卵の殻を食べるので、下手なものは使えません。
かみさんの理知的な判断には毎回脱帽。私だったら両面テープで貼り付けたかもしれません。
追記(2021.10.2):
「これじゃ説明が足りない‼」と言う方は、こちらの記事をご覧ください。
シュッと細くなる
2019.6.24
「蛹便(ようべん)」という言葉をやっと見つけました。お恥ずかしい限り。
デジタル大辞泉にはこう書いてあります。
さなぎから羽化するときに排出される体液。チョウなどの完全変態をする昆虫の一部にみられる。折りたたまれた羽を展開するとき、翅脈に体液を圧送するが、その余分な体液を便として排出するもの。羽化液。
これまでは蛹便のことを「下痢便」とか、「水様便」とか書いていました。
私以外にもそう書いている人は多いのですが、いい表現ではないので、正式には何と言うのだろうと思っていたところ。よかったです。
蛹便なら昆虫限定の専門用語であることがわかるでしょう。
と前置きが長くなりましたが、アゲハチョウの幼虫は蛹便が近づくとほっそりしてきて、蛹便をするとすぐにシュッと細くなることをご存じでしょうか。
このとおり。
このように蛹便が出てすっきりした青虫は一段としわが寄り、縮んで細くなり、蛹になる場所を探し始めます。
この青虫は珍しく、アクリルケースの中の枝で蛹化しました。
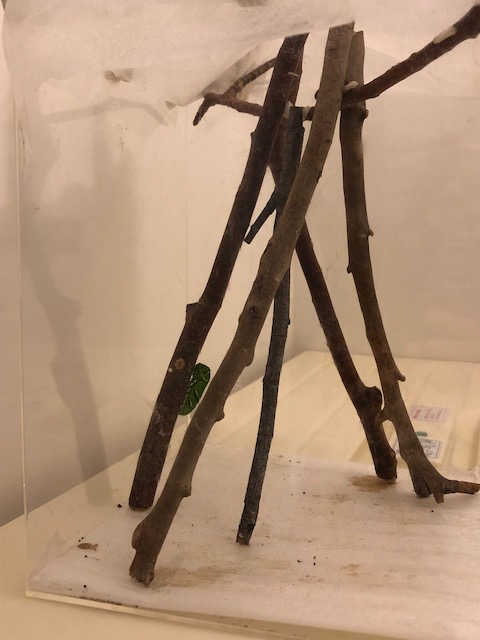
追記(2020.6.9):
蛹便は前蛹になる前の便ではなく、羽化する時の便でした。上記デジタル大辞泉の定義にあるとおりです。ちゃんと読んでいませんでした。大変申し訳ありません。お詫びと共に訂正させていただきます。
こちらの記事 に書いたとおり、当サイトの「蛹便」は別の言葉に置き換えます。但し、この記事はこの追記をしましたので、このままにしておきます。
落ち着かない
2019.6.25~26
前稿の冒頭に書いたとおり、ナミアゲハが夕方に羽化したので、そのまま翌朝まで放っておくことにしました。


大抵の場合、蝶は翅が乾くと少しの間飛び回り、その後おとなしく壁か天井にとまっています。
ところが、この蝶はLEDのカバーの周りをバタバタ飛び回り、全く落ち着きませんでした。

それで仕方なく手で捕まえて、虫かごに閉じ込め、黒い布で遮光。

こうしておけば、虫かごの中で暴れて翅を傷めることはありません。
久しぶりに翅をつまんだら、鱗粉で指が真っ黒に。うまく捕まえられず、何度もつまんでしまい、申し訳ないことをしてしまいました。
それでも、翌朝元気に飛び立っていったとのこと。
よかった。
あとがき
生き物は何でもそうだと思いますが、アゲハチョウもなかなか奥深いですね。
趣味で飼育しているだけでも、いろいろな発見があります。
アゲハチョウ 育ててみれば 奥深い
すみません。そのままでした。
2019/6/27,2022/2/2
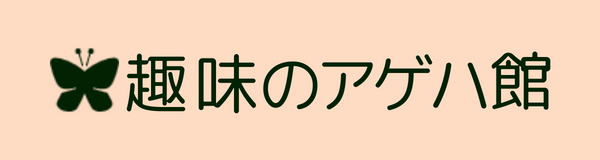

コメント