ツマグロヒョウモンの幼虫がいますか?「これはどうやって育てたらいいんだろう」「何を食べるんだろう」「トゲトゲでグロいけど毒は無いのか」と思っているところかもしれません。
「ツマグロヒョウモン 幼虫」の検索ボリュームは「モンシロチョウ 幼虫」より多く、飼育している人は多いようです。アゲハチョウとは蛹化の仕方が異なりますが、育て方は難しくありません。
この記事では幼虫の飼育環境や食べ物、蛹化、羽化までの世話について、さらにツマグロヒョウモンの毒性の有無、似ている昆虫、天敵、活動時期、越冬に関することまで、幅広く解説します。
この記事をご覧になれば、ツマグロヒョウモンのことは大方わかります。
- ツマグロヒョウモン幼虫の適切な飼育環境
- ツマグロヒョウモン幼虫の食べ物の種類や注意点
- 幼虫~蛹~成虫の変態プロセスとその間の世話
- ツマグロヒョウモンの毒性、天敵、活動時期、越冬
ツマグロヒョウモン幼虫の育て方
ツマグロヒョウモンの幼虫を育てる際、事前に用意するものは以下のとおりです。
この記事では室内飼育を想定しています。
幼虫の飼育は脱走できない容器で
まず飼育環境ですが、ツマグロヒョウモンの幼虫は頻繁に食草を離れるので、ビン刺しはお勧めできません。

こういうのはだめです。容器に閉じ込めておかないと脱走は必至ということ。
我が家ではこんな容器に入れています。


これの利点は観察しやすいこと。
難点は通気性が悪いことですが、餌の交換や糞の掃除で頻繁に開けるので、問題ありません。

確かキウイフルーツが入っていたケース
幼虫が病気にならないように、飼育環境は高温多湿を避け、衛生状態をよくしましょう。
ツマグロヒョウモン幼虫の食べ物
食べ物(餌)はスミレ、パンジー、ビオラなどのスミレ科植物です。
これはスミレの葉っぱを食べているところ。
パンジー以外でも普通に食べます。ご安心ください。
このように種も食べます。(^^;)
ホームセンターなどで売っている苗木は、農薬を使っている可能性が高いので、ご注意ください。
幼虫が蛹になるまでの世話
幼虫は孵化した後、通常は4回脱皮して、終齢幼虫になります。

脱皮直後はこのように突起全体が赤いですが、すぐに先端が黒くなります。
幼虫が動かない時はおそらく脱皮の準備中です。そーっとしておいてください。
脱皮してもアゲハチョウのような形状の変化はないので、齢数の判別は大きさで見当をつけるしかありません。
終齢幼虫はこれ。

大きさは4~5cm。
終齢幼虫になってから、餌は十分あるのに忙しくさまよい始めたら、おそらくワンダリング(蛹化の場所探し)です。蛹になれる場所を作ってあげましょう。
ツマグロヒョウモンは垂蛹型と言って、

このようにぶら下がって蛹になります。
ということで、幼虫がぶら下がれる場所を用意してあげましょう。
うちではこうしています。


蛹化用ケース。
四隅に割り箸を貼って、上に枝を渡しています。ふたに張り付かれるのが嫌なので。
(10倍速)
ぶら下がる場所が決まったら、落ちないように入念に糸を張り巡らします。
(5倍速)
無事蛹になりました。

よく落ちないね。
うちでは、前蛹の期間(幼虫がぶら下がってから脱皮するまで)は大抵12時間です。それが標準的な時間なのかどうかはわかりません。


左は脱皮直後。右は脱皮6時間30分後。
上部の鋲のような突起が金色だと雌、銀色だと雄と言われていますが、当てになりません。( 飼育日誌2141 )
蛹が成虫になるまでの世話
蛹化から羽化までの期間は夏場なら1週間前後。気温が下がると、それなりに長くなります。
我が家では10月30日に蛹化、11月20日に羽化したことがありました。
蛹は羽化が近づくと、

このように黒ずんできます。
この時は羽化の瞬間を動画に収めようと待ち構えていたのですが、ちょっと席を外した隙に出てしまいました。(泣)
ツマグロヒョウモンはアゲハチョウと違って、スルッと出てくるので、なかなか羽化の瞬間を見ることができません。


左が雄。右が雌。

わかりやすい。
成虫の飼い方、ユニークな特徴はこちらの記事でご覧ください。
蛹が落ちた時の救済方法
滅多にないことですが、蛹が落ちてしまったら、どうすればいいのか。アゲハチョウやモンシロチョウのように、蛹ポケットに入れるわけにはいきません。
救済方法に関してはこちらを参考になさってください。

画像の蛹は同じ垂蛹型オオゴマダラの蛹です。
蛹のおしりを木工ボンドで枝にくっつける人もいますが、接着剤を直接蛹につけるより、こちらのほうがいいでしょう。
ツマグロヒョウモン幼虫の毒性その他
ツマグロヒョウモンの幼虫に毒性はない
ツマグロヒョウモンはジャコウアゲハと違って、幼虫にも成虫にも毒性はありません。成虫の雌は毒があるカバマダラに擬態しているだけです。
幼虫は毒々しい様相なので、最初は触るのに抵抗があるかもしれませんが、

このように指に乗せても問題ありません。
全身にある棘のような突起は柔らかく、性格は温厚です。そもそも臭角はあるのか。いまだに見たことがありません。
ツマグロヒョウモンの幼虫に似ているのは何?
ツマグロヒョウモンの幼虫似ているのはジャコウアゲハの幼虫です。
ツマグロヒョウモンと同じく、棘のような突起に覆われた黒い体。と言っても、

このようにジャコウアゲハはずんぐりしていて、中央に白い帯状の模様があります。他の幼虫に比べれば似ていますが、違いは一目瞭然ですね。
ジャコウアゲハは幼虫にも成虫にも毒があります。詳細はこちらの記事でご覧ください。
ツマグロヒョウモンの天敵は他の鱗翅目と同じ
ツマグロヒョウモンの天敵は他の鱗翅目と同じです。
鳥、蜂、カマキリ、カメムシ、クモ、アリ、寄生バエ、寄生バチなど。
前述のとおり、ジャコウアゲハの幼虫と違って毒は無いので、普通に襲われます。
ツマグロヒョウモンの活動時期~幼虫の越冬
ツマグロヒョウモンの活動時期は概ね4月~11月。アゲハチョウより長く活動します。
アゲハチョウは休眠蛹になって越冬しますが、ツマグロヒョウモンには決まった越冬態がありません。つまり、休眠状態にならないということ。
と言っても、越冬できないわけではありません。ツマグロヒョウモンは小さい幼虫なら何とか寒さを凌いで越冬する、というのが正解のようです。
ツマグロヒョウモンの越冬に関しては、こちらの記事もご覧になってみてください。
ツマグロヒョウモンの幼虫【まとめ】
以上、ツマグロヒョウモンの幼虫について詳しく書きました。
ポイントは以下のとおりです。
ぱっと見グロいツマグロヒョウモンの幼虫。友人に見せたら、「なんだこれ」と言ったきり絶句。私も最初は触るのに躊躇しましたが、何の害もありません。

すごい可愛い。
一度、育ててみるのはいかがですか?
2022/9/26,2024/5/13
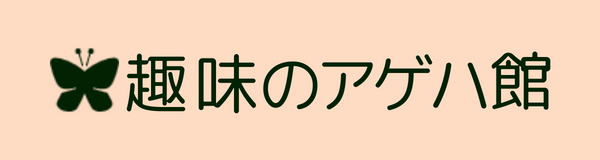



コメント